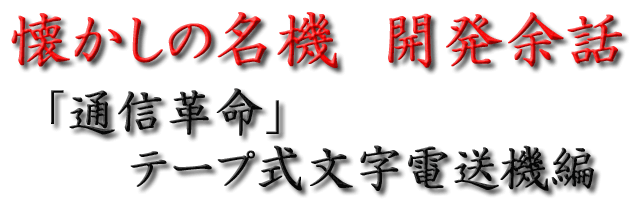
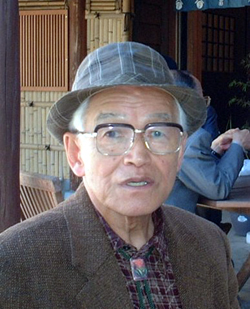 |
||
| 2005年9月 久貝 達也 |
||
この画期的な変換点に貢献したファクスが、昭和20年代から約10年間、わが社の経営の主力商品となっていた、 テープ式文字電送機です。時代の流れで当時を知る人も少なくなり、その存在すら忘れられかけていますが、 会社の歴史を語るには不可欠の商品ですので、それについて述べてみたいと思います。 | ||
|
ここで、テープ式文字電送機の要点を説明しておきます。 |
 |
|
|
|
||
| 昭和23年7月 | 北海道新聞展への出展 |  |
| 10月 | 福岡国体に、福岡−東京間に実用を兼ねたテスト。 (衣川、久貝立ち会う |
|
| 12月 | 本格的な量産開始。 | |
| 昭和24年4月 | 共同通信社通信回線に配備され実用開始。 | |
| ソ連からの抑留引揚者名簿配信に正確、迅速の威力を発揮した実績が高く評価されて、 報道各社への導入と拡大していったのです。 | ||
|
本年は戦後60年、旧松下電送の創業記念日の11月1日も60年の節目の年でもあります。 人生の歩みの一環として、書き残しておこうと考えていたところ、市橋会長から、是非との要望で、少し早めにまとめました。 | ||
|
参考文献 共同通信社35年史 松下電送30年史 | ||
| Copyright © 2019 パナソニック電送社友会 All rights reserved. |
| ページトップに戻る |